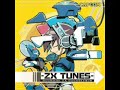カターニャ vs ローマ ハイライト
 3大テノール 世紀の競演 |
娘が赤ちゃんの時、毎日、朝から夜まで聞き続けた。とにかくお気に入りで、飽きることなく、何年、毎日聞き続けただろうか。3人が日本に公演に来たときどうしても行きたかったが、子供を連れて行くわけにもいかず、また、10万円のチケットに尻込みをしてあきらめた。その子供も大人になった。パバロッティはトリノオリンピックの開会式が最後の舞台となり、昨年の今頃亡くなった。
最近改めて聴いている。20年近く経とうと、やはり良い物は良い。3人のパリコンサートも秋にはお薦めです。 ドミンゴの粋さ、パバロッティの朗々とした天にも抜けるような声は筆舌に尽くしがたい。何度聞いても飽きることはないでしょう。聴くたびに感動し、そして、晴れ晴れとした気分にさせてくれます。 |
 ア・デイ・ウィズアウト・レイン |
伸びやかなメロディー、包み込むような歌声、厳しいアイルランドの自然の中で荘厳に謳い上げる様子が目に浮かび上がります。
(思い出) 『ENYA』の読みは『エンヤ』ではないようです。 英国でネイティブと音楽について話した時に『エンヤ』で通じませんでした。 『こいつらエンヤを知らんか』と思いましたが、そうではなく、 『ENYA』は『イーニャ』と読むのだそうです。 『ENYA』ファンで英国に行く予定の方はどうぞご注意ください。 |
 3大テノール 世紀の競演 [DVD] |
もはや今日、三大テノールも「商業化」してきているが、これは「イベント」として初めて三人が集ったもの。今後も4年おきに続くとはつゆ知らず、本日限りという気持ちで気迫あふれる名演奏に徹している。 その後のアメリカ、フランスでは、選曲が開催国に偏っていたが、本作品は全世界的な視点とオペラのマスターピースで構成されている。名曲「マレキアーレ」が入らなかったのは残念だが、メイキング編(別売)ではピアノを囲んで三人が楽しそうに熱唱しているので、そちらも必見。 舞台はローマの古代遺跡、音響の都合上2つのオーケストラを動員しているが、いずれも大迫力に寄与している。「星は輝きぬ」のバックとしてこれ以上ない最高の舞台である。 さらにCDには収録されなかったオーケストラのみの演奏が入っている。オペラで忘れてはならないヴェルディの曲は、ここでカバーされている。 |
 ROME[ローマ] コレクターズBOX [DVD] |
ローマ内乱という壮大な舞台を完璧な映像で再現していながらストーリーは『24』ばりのクライムサスペンス。
細部は書き換えられて正統な歴史物ではないのだが、ドラマなのだからとそれに目をつぶっても脚本がチープ。 愛と策謀がテーマらしいが、策謀と言えるほどの駆け引きは見られない。 誰もが近視眼的で、感情むき出しで、目先の利益や一時の感情に流されて行動している。 口を開けば「俺を裏切った」「侮辱した」「報復だ」。憎しみ、ねたみ、そねみばかりが 描かれている。問題が起きれば脅迫と暴力で解決。上から下まで、小人閑居して不善を為 すと言う言葉がぴったり合いそうだ。 確かに感情を中心に描くのはリアルなのかもしれないが、感情は人間の一面に過ぎない。 知性だとか、見識だとか、聡明さを見せてくれるシーンはほとんど無いのが残念。 カエサルは史実通り寛大さを発揮するのだが、彼の苦労や窮地が描かれていないため、 寛容さも単なる打算に映ってしまう。 現代を舞台にしたクライムサスペンスでなら妥当な脚本かもしれないが、期待していたためがっかり感は大きかった。 前半はまだ良いのだが、後半、元老院が機能しなくなると描写が個人に集中していき、 オクタヴィアヌスとヴォレヌスの周りのごたごたが交互に描かれるようになり、加速度的に 話のスケールが小さくなっていく。 しかし、それを補って余りある、とは言えないのだが、映像は素晴らしい。セットから小物まで非 常にこっていて、当時のローマが感動的なレベルで再現されている。宗教儀式、風俗、迷信深さ、奴隷の 扱いまでもが上手く当時の日常を描き出していると思う。 また脚本はともかく、出演陣の演技も素晴らしい。直情的だが唯一まともなプッロ、 すぐにキレる狂犬ヴォレヌス、バカで傲慢だがどことなく憎めないアントニウス、 威風堂々としたカエサル、小憎たらしいオクタヴィアヌス、最後まで野心が空回りしてい るアティア、生真面目さがにじみ出しているブルータスとキケロ、 強欲な奴隷秘書にやたらオーバーアクションのデブの広報官。 誰もが生き生きと演技していた。 |
 ザ・ローマ 帝国の興亡 DVD-BOX |
史実を分かりやすく、ドラマとしても面白い!この手のモノで吹き替え付きなのも良いです。
映像も素晴らしいのですが、馬に鐙が付いてるのにはガックリきました・・・ 鐙無しの騎兵と言うのはローマ史においてかなり重要な事だと思うので、後からCGで消すとか徹底してもらいたかった。 カエサルのハゲまで徹底しているというのに |
 ローマの休日 [DVD] |
物語を知らない人がまず購入するにはよいかもしれません。
本当に映像のすばらしさを知るには、さらに映像のよい版を購入するとよいでしょう。 特に、画質のよいテレビをお持ちの方は、古い画質の悪いDVDを見るのが苦痛になるかもしれません。そういう方は、最初から画質のよい版をご購入ください。 物語はよく知られたお話です。 |
 シャドウ オブ ローマ |
いやぁ私、古代ローマみたいなのまったく興味無かったんですが、たしかにおもしろい!残虐で出血びゅうびゅうですがなぜか爽快!潜入系のゲームも苦手ですがドキドキしながら下手なりになんとか進める難易度です。 最後のほうになると戦闘の難易度かなり高めになってきますが、ぶったおした時はガッツポーズですね! クリアした最近は嫁さんと喧嘩した後にストレス解消に雑魚をぶったぎってます! とにかくストレスたまってる人は買いでしょう! |
 バトルフィールド1942 ロード・トゥ・ローマ |
新しい伊軍などのフィーチャーは、専用のマップでしか 使えない。お金を払ってまで・・・というのが率直な感想。 5~6回プレイしたらお腹いっぱいかもしれません。 今回のカスタムゲームとして認識されるため |
 ローマ亡き後の地中海世界(上) |
「ローマ人の物語」15年間を通して塩野氏は、常に疑問を呈していた。「人類の進歩」なるものについて。
だから、ローマ人の帝国があれほど大をなし、かつ人類に多くの偉大な教訓を残した最大の理由を塩野氏は端的にこう表現した。 「人間という生き物の本質に、全く幻想を抱かなかったからだ」と。 だから、 全盛期の民主制アテネを見ても、民主主義の華やかさに惹かれることもなかった。 民衆に現実以上の認識能力を要求することが前提の民主制の欠陥に、無意識にしろローマ人は気づいていた。 ローマ人は、統治能力を問題にしても、統治理念には拘泥しなかった。 また唯一絶対の正義や神意、真理の追求などという不毛な思索には、全く興味がなく、 だから、 異なる宗教や文化を根絶する発想など、どこを押しても出てこなかった。 しかし、ただの一行で書けるこのことを、その後の人類は全く理解出来ないまま、二千年が過ぎてしまったのではなかったか。 現代の我々とて、同じだ。 異なる一神教同士というどちらかが消滅しない限り本質的に解決がありえない争いは、現在に至るも出口すら見えない。 宗教の狂信には一見無縁の我々日本人も、政治においては結果よりプロセスに拘り、統治能力よりも空虚な統治理念に拘泥する愚から逃れられていない。特に安全保障については、もはやほとんど宗教的な反応しか出来ず、現実を思考する能力すら喪失してしまった。(元々、民族性として不得手ではあったが) 塩野氏は、冷徹に、辛辣に書く。「平和は余りにも重要で、だからこそ平和主義者には任せてはおけない」と。 「ローマ亡き後の地中海世界」は、現実的なローマ人亡き後の、異なる二つの文明の不毛な争いの物語である。 そこに、ローマ人の物語の10巻までにあった高揚感や充実感はない。人間の救い難い狂信、妄信、無邪気な無知と偏狭な善意が招く、無常観が漂う暗黒の中世史である。ゲルマン民族の侵略を「民族の大移動」等と偽善的な表現をせず、「蛮族の侵入」とはっきり書いた塩野氏である。今回も、その冷徹な視点は健在で、はっきりと「暗黒の中世」と言い切っている。 しかし、ローマ帝国史の高揚感、充実感がなくても、別な意味の歴史の面白さ、というか大切さが本書にはある。 これもまた人間の所業なのだ。こういう人間と歴史の現実を直視することこそ、大切だと思うからだ。 特に我々日本人ほど、過去の歴史を冷徹に直視することが下手な民族も少ないと思えば、尚更本書のメッセージの重要性も増すというものである。 |
 ローマ人の物語 (33) (新潮文庫 (し-12-83)) |
待望の、「ローマ人の物語」の文庫最新刊です。
このシリーズ、前半ほど波乱に富んだ魅力的な人物は出てこないんですが(史実とその分析なんで、当然ですが)、それでもとても面白くて含蓄に飛んでいて自分にとって滋養になる作品なので、出るたびに古代ローマの世界にはまり込んで読んでしまいます。 さて。 本作では3世紀のローマが舞台で、このあたりからローマは完全に崩壊へと向かっていきます。それまでは敗者を同一国家の帝国内に同化して肥大化させてきたローマが徐々に潰れていく過程が描かれています。この33巻はその序章ということで、どうしてローマが滅んでいったのかということをその当時の3人の皇帝を順々に紹介していくことで浮き彫りにしています。 たとえば、カラカラテルメで有名なカラカラ帝(ちなみにテルメは浴場です。なので宝塚にあったカラカラテルメはカラカラ帝の浴場という意味だったわけですが、イタリアからきた人はどうしてこんなものが日本にあるのか首をかしげたでしょうね。感覚としては、日本人がヨーロッパにいったら、その片田舎にいきなり「秀吉太閤の湯」みたいなお風呂屋さんがあるようなものですから)。 彼は「すべてのローマ帝国領内の人間はローマ市民権を得る」という新法を出しますが、これがいけないと塩野七生さんは書きます。一見すると、これはローマの敗者同化主義の延長で、今まで同様の権利委譲に見えるし、ヒューマンなものだが、これによって逆にローマ軍の中核である市民の志気が下がり、財政上の問題も出て来た。人間は「取得権ならば頑張るが、既得権になった時点で頑張らなくなる」という視点からこの法によってかえってローマ全体の一体感が薄れたのではないかという風に示しています。 このあとタイミングも悪くローマは、長年の宿敵パルティアを倒して大ペルシアの復活をもくろむササン朝ペルシアとの戦争に突入してしまうんですが、その前段階としてのパルティアとの戦争に弱腰であったとしてカラカラ帝は暗殺され、それを指揮していたのではないかといわれるマクリヌスが皇帝としてたつも、戦争をシリアの放棄という形で講和した(このあたり、弱腰だとして前皇帝を非難して暗殺した本人がそうなっちゃうのが少し理解に苦しむ人ですが)ということで、マクリヌス自身が暗殺で殺されてしまいます。反動のような形でカラカラの血をひく、ヘラガバルスやアレクサンダルが皇帝にたつもののじわじわとローマは崩れていきます。ヘラガルバスなどは、男色でしかも自分が受けの方であったことを公然としていたこともあって侮蔑の上で殺されてしまいますし、アレクサンドルもガリアとの戦いでの弱腰を非難されて暗殺されます。 こうしてみてみると、時代が要請したこともあるかも知れませんが、マッチョではないということで少しでも弱腰を見せるといかに皇帝であろうと暗殺されたり殺されたりしていく、しかも前線で配下の将軍や近衛軍に殺されたりしていくというパターンになっていきます。やはり軍部が力を持つと恐ろしいことになっていくのだなぁとしみじみ思います。 これよりも古代のローマでも内戦めいたこともあったし、元老院と皇帝の戦いや、皇帝ら有力貴族同士の権力闘争もありましたが、あくまで巨頭同士の戦い的なものが多かったのが、このあたりの皇帝は絶大な権力をもつといえども、気にいらなければ殺されるような危ういものになっていってて、このあたり通史としてローマ国が建国されたあたりからずっと読み進めてきただけに感慨深いです。感想というよりは紹介みたいになってしまいましたが「ローマ人の物語」はやはり面白いです。 |
 ローマ人の物語 32 (32) (新潮文庫 し 12-82) |
偉大な皇帝の時代は終わり、人間臭い皇帝たちが、人間臭く死んでいく。
いや、偉大な皇帝たりうる資質を持った皇帝も志半ばで、 ささいな躓きから命を落としてしまう。 まるで、老いはじめた帝国がそれを拒んでいるかのように 自然の成り行きから良かれと思い発せられた法が、まわりまわって 社会の衰退を加速させ、世に閉塞感がただよう。 そして不安を募らせた人々は麻薬を求めるように宗教に走る。 繁栄する帝国よりも、迷走する帝国の方が 現代社会への教訓は多い |
人気動画
|
Loading...
|